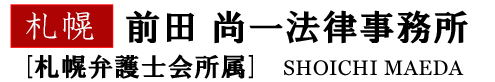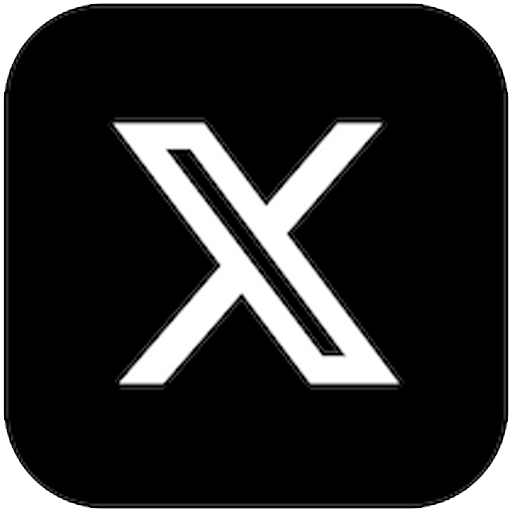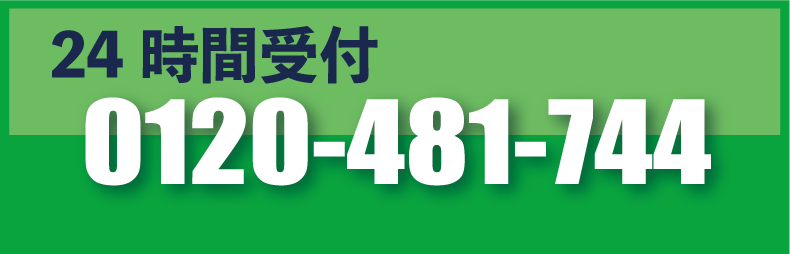労働契約の成立(採用内定)
わが国では、一般には、採用内定から就労に至るまでかなりの期間を有することが多いです。
そこで、採用内定と労働契約の成立との関係がいかなるものかが問題となります。
この点に関しまして、採用内定の法的性質として、最高裁は、企業の募集が労働契約締結の申し込みの誘因であり、労働者の応募は労働契約の申込みであって、採用内定通知はこれに対する承諾であるとしています。
そして、採用内定は、特殊な労働契約であり、始期付解約権留保付労働契約とみなすべきとしています(大日本印刷事件 最判昭和54年7月20日)。
そうしますと、一般的には、労働契約の成立時期は、採用内定通知の到達時ということになりますが、具体的な採用内定の性格等により、個別に解釈すべきと考えられています。
採用内定は、特殊な労働契約とされていますから、採用内定の取消についても問題となります。
つまり、裁判所によれば、採用内定により始期付解約権留保付労働契約という特殊な労働契約が成立しているのですから、採用内定を取消すことは、留保解約権行使の適法性の問題となります
これにつきましては、採用内定を始期付解約権留保付労働契約とするのですから、通常は、採用内定段階で労働者に明示されている解約事由が生じた場合に解約がなされることになります。
この解約事由は、抽象的な一般条項により記載されていることが多いため、内定取消がなされた場合につきましては、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる、としています(大日本印刷事件)。
また、中途採用者につきましても、基本的には、解約権留保付労働契約として、上記と同様の判断枠組みで判断されていると考えられます(オプトエレクトロニクス事件 東京地判平成16年6月23日等)。
そして、採用内定取消は、債務不履行責任や不法行為責任が認められる可能性があります(パソナ事件 大阪地判平成16年6月9日等)。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。