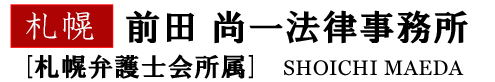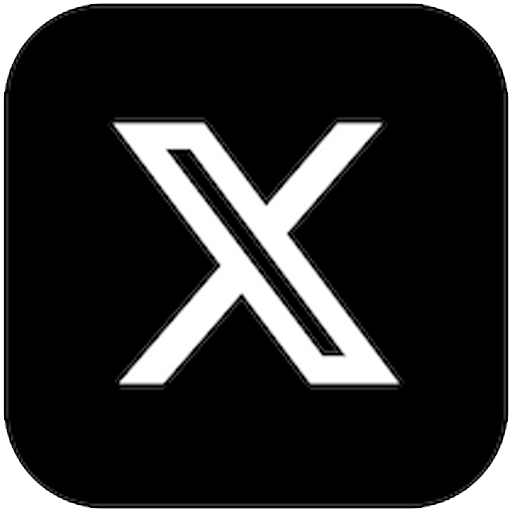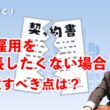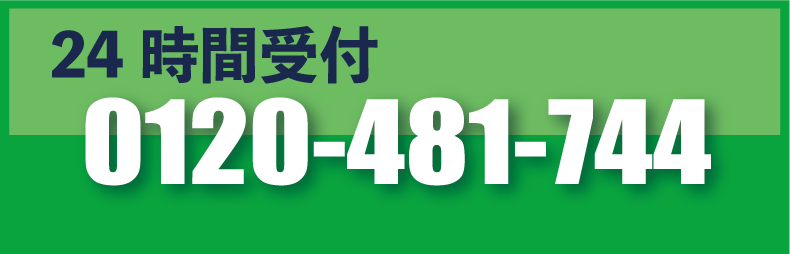男女賃金差別の禁止
男女賃金差別の禁止
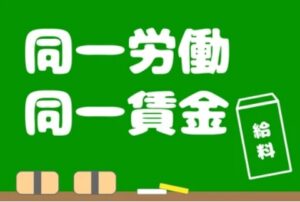
1(1) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性との間で差別的取扱いをしてはなりません。これは労働基準法4条に規定されています。罰則規定も設けられており、違反すれば、六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます。また、民法上の不法行為にもあたり、使用者は損害賠償責任を負います。仮に就業規則でこのような規定を設けた場合、その就業規則は無効となります。
(2)このように、法は、女性に対する賃金差別には厳しい態度で臨んでいます。では、使用者が女性に対していかなる待遇をしたときに賃金差別となるのでしょうか。労基法4条の規定に沿って見てみます。
2 もう一度条文をみると、使用者は、労働者が「女性であることを理由とし」て、「賃金について」、男性と「差別的取扱い」をしてはならない、とあります。
(1)「賃金について」
条文中に「賃金について」とあるように、本条は賃金についてのみ規定しています。ここでいう賃金とは、月給だけではなく、退職金や住宅手当、家族手当も含まれますから、たとえば、男性従業員だけ家族手当を支給するなどすれば、本条違反になります(仙台高裁決定平成4年1月10日)。
他方、採用や昇進についての男女差別は本条では禁止されていません。また、採用上や昇進上で差別を受けたことにより賃金格差が生じたような場合も、本条の問題にはなりません。
しかし、職位と賃金が結びついている場合に、女性に対する昇格差別をすることが、女性に対する賃金差別と同視されることがあります(横浜地判平成19年1月23日)。
(2)「差別的取扱い」
給料別の賃金体系、男性は月給制なのに女性は日給制、男性のみに住宅手当、などがこれにあたります。
また、女性を不利に扱う場合だけでなく、有利に扱う場合もここでいう「差別的取扱い」にあたります。
(3)「女性であることを理由」とする差別
女性労働者は能率が悪い、勤続年数が短い、主たる生計の維持者ではないとの理由を持ち出し、実際にそうであるか否かに関わりなく差別を行うことは、本条違反になります。
他方で、一般職か事務職かなど、性別以外を理由に賃金に格差を設けることは、本条違反にはなりません。もっとも、男性は一般職、女性は事務職として採用する賃金体系を設けている会社において、勤続年数も長く一般職と同様の職務を行う女性事務職が、同程度の職務内容や困難度の男性一般職との間に相当の格差があった例では、本条違反にあたるとした判例があります(最高裁決定平成21年10月20日)。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。