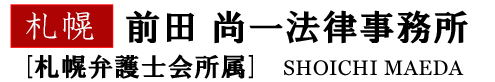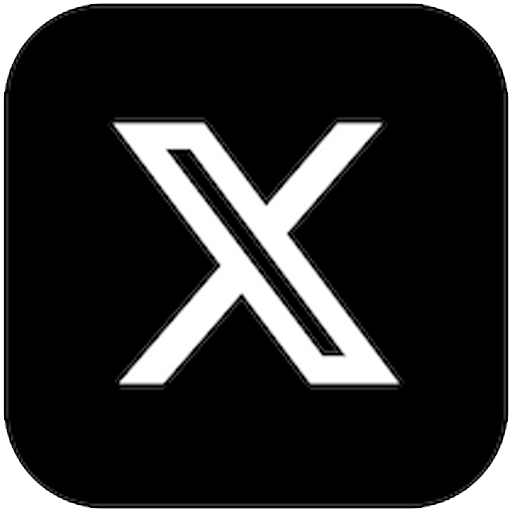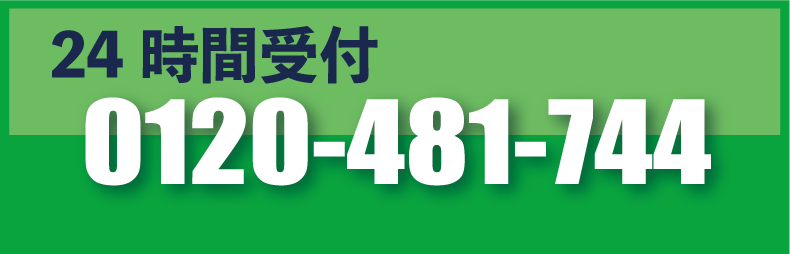解雇・退職勧奨は慎重に!
Contents
解雇・退職勧奨でお悩みの経営者の皆様へ
リスクを最小限に抑え、企業の未来を守るためのアドバイス
「この社員にはもう退職してもらうしかない…」
そう思った瞬間、眠れぬ夜を過ごした経営者の方も多いのではないでしょうか。解雇や退職勧奨は、会社にとって重要な決断である一方、慎重さを欠けば多額の損害賠償請求や労使紛争に発展するリスクを伴います。
日本の法律は、解雇について非常に厳格な基準を設けています。「能力不足」や「勤務態度の不良」といった理由だけで解雇を進めた場合でも、適切な手続きが欠けていれば無効と判断されることも珍しくありません。例えば、業務命令違反を理由に解雇したが、必要な警告や改善の機会を与えなかったために無効とされたケースもあります。
一方、退職勧奨もまた注意を要します。不適切な方法で進めた場合、「退職強要」として訴えられるリスクがあります。特に、退職願を書かせたものの後で撤回され無効とされた事例や、従業員を別室に隔離して圧力をかけたことが慰謝料請求に発展したケースなどがその典型例です。
では、どのようにすればリスクを最小限に抑え、円滑な解決を図れるのでしょうか?
解雇や退職勧奨を成功させるための3つのポイント
-
公正かつ妥当な手順を踏む
解雇や退職勧奨を進める際には、適切な就業規則に基づいた事前警告や改善の機会を設けることが重要です。また、従業員に意見を述べる機会を提供し、公平性を確保する必要があります。 -
法的根拠と証拠の確保
解雇や退職勧奨を正当化するには、合理的な理由を示す具体的な証拠が必要です。たとえば、業務上の問題やトラブルの経緯を日々記録し、万が一の紛争に備えることが大切です。 -
専門家のサポートを活用する
労働問題に精通した弁護士に早い段階で相談することで、適切な対応方法を見極められます。法律だけでなく、人材マネジメントや労務管理の観点からも助言を受けられるのは、弁護士に相談する大きなメリットです。
私たちが提供するサポートとは
当事務所では、35年以上にわたる実績をもとに、解雇や退職勧奨に関する問題を円滑に解決するお手伝いをしてきました。経営者の皆様に寄り添い、法的リスクを最小限に抑えるサポートを提供します。
当事務所の強み
- 豊富な経験:多数の解雇・退職勧奨案件を解決してきた実績
- 早期解決:トラブルが大きくなる前に適切な対応を提案
- 分かりやすい説明:法律用語を噛み砕き、誰でも理解しやすい形でアドバイス
- 長期的な支援:継続的なパートナーシップを通じた信頼構築
まずはご相談ください
解雇や退職勧奨の問題を一人で抱え込む必要はありません。早期に専門家に相談することで、企業経営の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐことができます。当事務所は、経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう全力でサポートします。
トラブルが大きくなる前に、ぜひお気軽にお問い合わせください。
[お客さまの声]
〇病院代表者・男性・60代
労使関係に関わる問題で裁判となると微妙な案件について経験豊富な先生の巧みな交渉術で納得のゆく解決にまとめていただきました。クライアントに媚びない話し方に私は信頼を置きました。
〇会社専務(代表者後継予定)・男性・40代
会社は、札幌以外の地方都市にありますが、先生とは顧問契約を結び、一泊二日で札幌に赴き、毎月一度のコンサルを受けさせてもらっています。
話は多岐に渡りますが、毎日仕事に追われている中で現場を離れ、私なりのリラックス、ストレス解消の機会にもなっています。
さて、お付き合いの始まりは、もう10年以上前になります。
父の経営する会社で、現場従業員のAの解雇問題で、労働組合が結成されました。 私は専務になったばかりのころで満28歳のときでした。 社長である父が側近として雇ったBが、本人が言うほどに営業の成績を上げることが出来ないことから、父との関係が悪くなっていたころに、ちょうど解雇問題がおきたのです。 Bが音頭をとって、他の従業員ほとんどを引き入れ、地元の上部団体に駆け込み、組合を結成し執行委員長となったのでした。
2回目の団体交渉から私が対応することになり、ほとんど一人で団体交渉に臨むことになったのです。 団体交渉で、相手をするのは組合員となった従業員だけではありません。もう60歳近い闘志を始めとする数名が上部団体からの会社に乗り込んできて、数々の要求をしてきたのです。
当初はどのように対応したらよいか全くわからず、問題解決のため真正面から対応しようとしたのですが、10数名からただただ罵倒される日々が続いたのでした。
正直、その日の団体交渉を終え、家に帰って大好物のビールを飲んでも美味しく感じず、酔うこともできず、眠れない日々が続きました。
そのようなとき、信頼できる方の紹介で先生に対応をお願いし、同席してもらうようになり、流れが変わりました。
私だけのときは、組合はただただ罵倒して一方的に有利な要求を何か私に約束させようとばかりしていました。 先生が出席するようになってから、そうもいかなくなりました。 すると今度は、手を変え、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせとか、会社からすると本論とは関係がないと思われることばかりを要求してきました。 2、3か月綱の引き合いはありましたが、先生には、2、3度出席してもらった結果、社長が出席することも、決算書を提出することもなく、解雇問題については、妥結することができました。
しかし、一旦組合ができた後は、何を決めるにも組合を通せということになり、賃上げ時期になると春闘で団体交渉を繰り返すということになりました。
一度は、組合が突然ストを行うといって,シンパが何十人も会社の回りに集まったこともあります。しかし、会社としても大変でしたが、そのときも一応の手配をし、組合の思うがままにはならないよう対応できました。
三度、労働委委員会までいったこともあります。
その場でも、組合側は分が悪くなると、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせと言い出します。 このときも、上手く対応していただき、このような相手方の要求に応じることなく、会社が想定した内容で解決することができました。
結局、その後まもなく、Aは個人的理由で退職しました。
その後、Bと他の組合員が組合費のことで対立したとのことで、B以外の組合員全員が組合を脱退しました。
まもなく、病気を理由に会社をさぼっていたことがばれたBは、会社を退職しました。
そのため、組合は自然消滅し、今は存在していませんが、労働問題は全く発生していません。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。