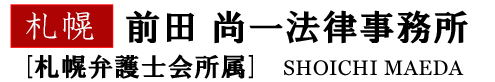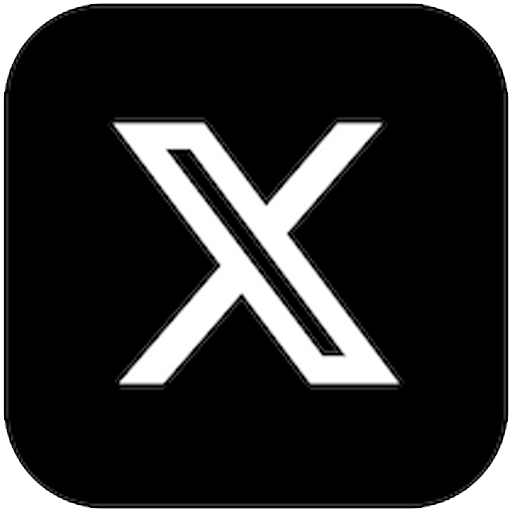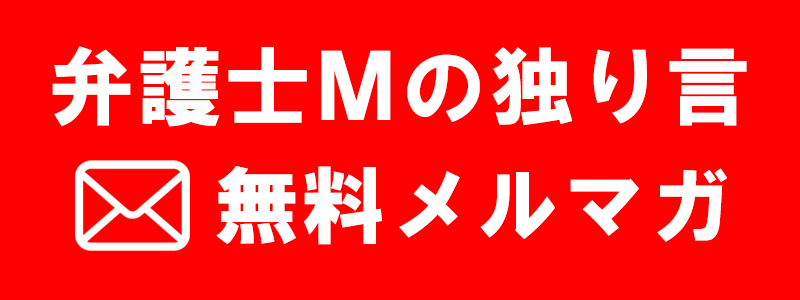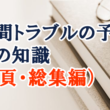配転:従業員が転勤を拒否したケース:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
配転とは?
配転とは、従業員の配置の変更であり、同一企業内での労働者の勤務地または職種・職務内容の相当長期にわたる変更をいいます。
その中で、勤務地の変更を転勤といい、職種・職務内容の変更を配置転換といいます。
配転は、実体法上の根拠はなく、主として就業規則に基づき行われて来ましたが、これは、労働者の能力・地位の発展や雇用を維持した上で労働力を調整する方法でもあります。
しかし、私生活やキャリアに影響を及ぼすことでもありますので、利害調整が必要となります。 そこで、配転命令の根拠と限界が問題となります。
配転命令の根拠につきましては、裁判所によれば、就業規則、労働協約に包括的配転命令条項が存在すること、そしてこれと異なる労働協約上の合意の不存在、そして労働契約が成立した際に勤務地を限定する合意がなされなかったことを根拠として、配転命令を認めたものがあります(東亜ペイント事件 最判昭和61年7月14日)。
つまり、就業規則に包括的配転命令条項が存在しても、就業規則とは別段の合意をした場合は、使用者は、労働者との個別の合意がない限りは配転命令をし得ないこととなります(労働契約法7条但書)。
そして、職種変更の場合におきましても、勤務地変更の場合と同様の判断がなされています。 配転命令権の限界 配転命令が認められる場合であったとしましても、使用者は権利の行使を濫用した場合には、無効となります(労働契約法3条5項)。
具体的には、配転命令について業務上の必要性がない場合、業務上の必要性がある場合に配転命令が不当な動機・目的がある場合、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある場合などには、配転命令権の行使は権利の濫用となるとされています(東亜ペイント事件 昭和61年7月14日)。
そして、具体的事情を判断するにあたりましては、配転命令が権利濫用と評価される場合は少なかったと考えられます。 ただし、最近では、勤務地・職種限定の合意が認められない場合であっても、勤務地・職種限定に対する労働者の相当な期待がある場合に関しましては、これに配慮すべき信義則上の義務を濫用判断に反映させ、また、配転にあたっての手続、説明の妥当性を考慮する裁判例があります(日本レストランシステム事件 大阪高判平成17年1月25日等)。
また、今後は、これら判断基準も、仕事と生活の調和の方向へと修正されていくとも予想されており、企業により人事管理も、育児のための必要性や家族の一体性などに対して丁寧な配慮を必要とされていくと考えられてきています。
従業員が配転を拒否
1 使用者には、人事権として労働者の職務内容や勤務地を決定する権限があります。通常は就業規則に「業務上の都合により転勤等を命じることがある」などと定められていますから、配転命令権自体が問題となることはあまりありません。使用者はこの配転命令権に基づき、従業員に転勤を命ずることができます。
2 しかし、従業員から転勤を拒否してくる場合があります。そのような場合、会社の転勤命令が認められなくなることもあります。例えば、次のような場合には、転勤を命ずることができません。
- 勤務場所を限定する合意がある場合
労働契約時、勤務場所を特定する合意があるような場合には、転勤を命ずることができません。また、採用時に従業員が「家庭の事情で当地以外には転勤できない」と明確に述べたにもかかわらず、会社側がそれを否定しなかった場合などのように、状況によっては黙示の合意が認められる場合もあります(大阪地裁判決平成9年3月24日)。
- 労働契約上の勤務場所を限定するとの取り決めがなかったとしても、転勤命令が権限濫用として認められない場合
たとえば、重病の家族の世話がある場合、高齢の親の介護がある場合などに、その従業員を遠隔地に転勤させることは、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を労働者に負わせる配転命令であるとして、会社側の転勤命令の権利濫用とされる場合があります(札幌地裁決定平成9年7月23日)。その他にも、不当な動機によってされた配転命令などが権利濫用とされるます。
一方で、共稼ぎや子の教育等の事情で夫婦別居をもたらすような転勤命令は、職務上の必要性があり、手当も十分な場合などには認められる傾向にあります(東京高裁判決平成8年5月29日)。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。