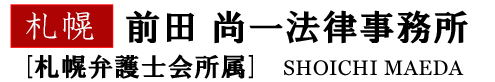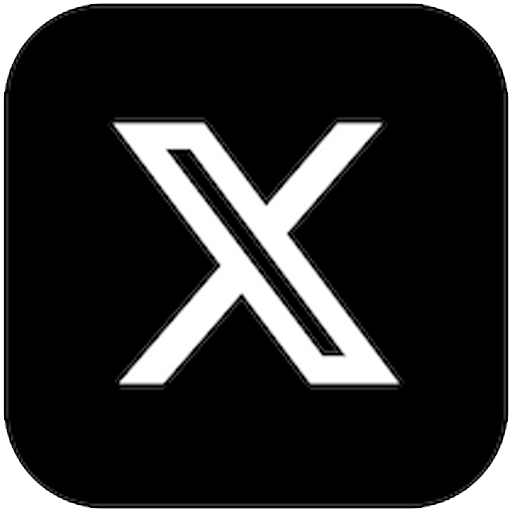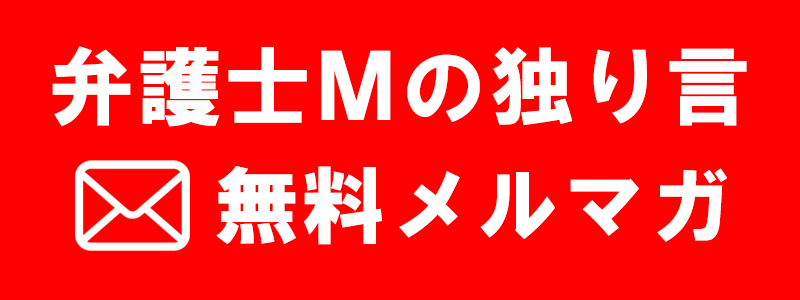懲戒処分原則(2)
懲戒処分諸原則
懲戒処分は労働者に大きな不利益を与えます。 そこで、懲戒処分につきましては、懲戒処分の有効性に関しまして、各処分に共通する諸原則が存在します。
具体的には、
(1)懲戒処分の種類・事由等が就業規則に定められ、(国鉄札幌運転区事件 最判昭和54年10月30日)、周知されていること(フジ興産事件 最判平成15年10月10日)
(2)懲戒の対象となる具体的事実が就業規則の懲戒事由に該当していること、
(3)不遡及・一事不再理の原則、
(4)相当性の原則、
(5)適正手続の原則です。
以下、(1)乃至(5)について説明します。 また、労働契約法15条におきまして、懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、懲戒権の濫用として無効とされています。
(1)に関しましては、就業規則が、法的規範としての性質を有し拘束力を生ずるためには、その内容を事業場の労働者に周知させる手続がとられていることが必要とされています。 裁判所によりますと、懲戒解雇処分当時に就業規則が存在しなかった場合には、懲戒処分は無効とされていますし(十和田運輸事件 東京地判平成13年6月5日)、就業規則に定められていない種類の懲戒処分はできないとされています(アメリカン・スクール事件 東京地判平成13年8月31日)。
(2)に関しましては、懲戒の対象となる具体的事実は、就業規則の定める懲戒事由に該当し、かつ、客観的に合理的な理由(労働契約法15条)があると認められなければなりません。 また、懲戒解雇につきましては、使用者は本人の請求があれば懲戒解雇事由を記載した文書を遅滞なく交付しなければならないとされています(労働基準法22条)。
(3)に関しましては、懲戒処分は制裁措置ですので、罪刑法定主義類似の原則として、不遡及・一事不再理の原則が妥当すると考えられています。 裁判所によりましても、懲戒解雇事由に関する規定は限定列挙であり、当該懲戒解雇の直後に設けた懲戒事由をもって、懲戒処分の根拠とすることは許されないとしています(富士タクシー事件 新潟地判平成7年8月15日)。 また、過去に懲戒処分の対象となった行為について、重ねて懲戒することはできず、過去に懲戒処分の対象となった行為について反省の態度が見受けられないことだけを理由として懲戒することもできないとしています(平和自動車交通事件 東京地決平成10年2月6日)。
(4)に関しましては、懲戒処分は、労働者の行為の内容、程度に照らして均衡のとれたものでなければならいとするもので、労働契約法15条に相当性の原則が示されています。
相当性は、同じ規定に同じ程度に違反した場合には、同じ程度の懲戒処分がなされるべきであるという公平性の要請があると考えられています。 また、従来黙認されてきた規律違反行為につきまして懲戒処分をする場合には、事前に労働者にその旨を周知・警告しておくことが必要であるとされています。
裁判所の判断におきましても、合理性、相当性判断につきまして、処分が他の関係者の処分と比較して極めて重いことも考慮して諭旨解雇を無効としたものもありますし(日本交通事業者事件 東京地判平成11年12月17日)、過去の処分との均衡も考慮して懲戒解雇を無効としたものもあります(西武バス事件 東京高判平成6年6月17日)。
(5)に関しましては、就業規則や労働協約により、諮問手続や弁解の機会付与手続、労働組合との事前協議、事前同意等が定められている場合には、定められた手続を経なければなりません。 定められている所定の手続を経ないでなされた懲戒処分は原則として無効とされるか、懲戒権の濫用となります。 裁判所による判断につきましては、就業規則や労働協約に手続規定が定められていない場合に、その場合であっても弁解の機会付与手続は必要と判断したものと、弁解の付与手続を不要としたものが存在します。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。