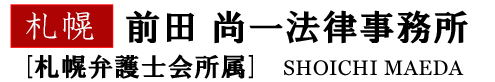【使用者側弁護士前田尚一(札幌)の視点】使用者側から見た「労働審判手続」
「申立書が届いたが、どのように対応すれば良いのか?」
労働審判を起こされると、使用者・経営者の方々は、言い分があるかどうかはともあれ、まずはうろたえるというのが通例です。
従業員、元従業員の言い分は、
「突然、解雇されてしまった。」「未払残業代がある。」「退職金を払ってもらえない。」などなど様々です。
「裁判官と労働関係の専門家が、3回以内の期日でトラブルの解決にあたります!」と説明されても、使用者・経営者側としては、具体的対策がはっきりしない、というのが実際です。
労働審判の申し立てられた使用者側・経営者側の対応について,わかりやすくご説明いたします。
使用者側から見た「労働審判手続」とは?

経営者は、労働審判手続を申し立てられた時点で既に負けている!!、
ご相談を受けるとその場で直感的に、そう言うほかない事案が少なくありません。
ところが、ほとんどの場合、当の経営者ご本人はそうは思っていないというのが実際です。
ここのところをきちんと認識せず適切な対応をとらなかったため、敗訴の審判を告知されてしまった上、そのまま放置し、売掛金を差押えられて慌てふためいて、当事務所に相談に見えた経営者がおられました。
『弁護士』の仕事は、“クライアント(依頼者)との協働作業”である、と考えている私としては、労働審判について依頼していた弁護士との間で、それまでどのような関係を構築して事を進めていたのか、全く理解できないところです。
ここのところをきちんと認識した上で適切な対応をとってこそ、一つの事件として発生した労働審判の解決が図られるだけではなく、それまでの労務管理の不備の改善が図られ、引いては、経営全般についてよりよいマネジメントの実現への糸口を掴むことができます。
ところで、労働審判手続については、 裁判所ウェブサイトで、次のように説明されています。
(引用始め)
労働審判手続は、解雇や給料の不払など、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としています。
労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
(引用終わり)
以上の説明は、裁判所の説明であるだけに、正確に要領良くまとめられています。
しかし、あくまで中立的な説明ですので、経営者の立場で、制度をどのように理解し、具体的に対応していくのがよいのかをイメージすることができないかもしれません。
そこで、ここでは、経営者の立場から労働審判手続の理解いただき、対応すべき方法を
ご説明することにいたしましょう。
まずは、裁判所の作成した「労働審判手続の流れ」の図(こちらをクリックしてください。)を御覧いただきながら、もう一度だけ、上記の裁判所の説明をご一読ください。
そして、次の、労使間紛争に悩む経営者A氏が、経営者側で労働問題を扱っている当事務所に相談に訪れた場面をお読みください。
A氏 裁判所から労働審判手続申立書等が送付され、出頭するよう呼び出されました。
前田 労働審判手続は、労働者と事業主との間に生じた労働紛争について、実情に応じた柔軟な解決を迅速・適正かつ実効的に図るため、2006年から始まった制度です。全国で年間3300~3700件ほどの申立てがあります。
1人の労働審判官(裁判官)と労働関係の専門的な知識経験を有する労働審判員2人で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で事件の審理を終えてしまいます。
まずは話し合いでの解決を目指して調停を試みますが、調停で解決できない場合は労働審判で解決案の提示をします。納得できなければ異議の申し立てをできますが、法律に従って申し立てをしないとその内容で確定するため、相手方は強制執行が可能となります。
ちなみに、経営者側の方は、労働者からの申立てを受ける場合ばかりを想定されますが、使用者も、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、労働審判手続を申し立てることができます。
労働者、使用者いずれからの申立てについても、法律で定められたとおりにしなければ、審理に入らないまま、申立ては却下されます。また、申立ては、労働審判が確定するまでは取り下げることができます。
A氏 労働審判事件は、「調停成立」か、「労働審判」で終了するのですね。
前田 労働審判手続は、労働紛争が労働者の生活をかけた紛争であるとの前提で、紛争の迅速で集中的な解決を図る仕組みです。そして、当事者の話合いによる調整が紛争をより迅速に実質的に解決するものであることから、労働審判委員会は、まずは話合いによる解決を試みます。これが成功すれば、「調停成立」として事件終了です。7割以上の事件が調停成立によって終了しています。
このような調停がまとまらない場合に、労働審判委員会が、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断として、「労働審判」を行います。労働審判委員会は、労働審判で、当事者間の権利関係の確認・金銭の支払等を命ずることができるばかりではなく、相当と認められる事項を定めることができるとされています。民事訴訟手続での裁判所の判断(判定)である判決ではすることができないような、極めて柔軟な判断をすることが可能となっています。
例えば、労働審判委員会としては、解雇無効の心証を得たが、職場復帰が実際には困難であるような場合、退職の確認及び金銭解決の審判をする場合もあるということです。
A氏 この上なく素晴らしい制度のように見えますが?!
前田 以上の解決を、原則として3回以内の期日で審理を終結する手続の中で目指すわけですから、労働審判による解決が適切なのは、解雇理由が単純な解雇事件や、賃金・退職金事件に限られることになります。
労働審判委員会は、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、事件を終了させることができるとされています。労働審判法の条文の番号をとって、「24条終了」と呼ばれています。24条終了となると、そのまま民事訴訟に移行することとなります。
要するに、制度としても、難しい事件、複雑な事件は、労働審判委員会の手に負えないものが想定されていることに加えて、労働関係に関する専門的な知識と経験とはいっても、労働審判委員会のメンバーそれぞれのレベルはいろいろで、話し合いで解決させる技能が優れているかどうか、相当と認められる事項をきちんと見抜ける眼識を備えているかは、保証の限りではありません。
A氏 労働審判手続の仕組み・流れはよく分かりました。しかし、先月に退職したばかりの従業員によるものなのですが、言い分は全く納得できません。まずは何をすべきでしょうか。
前田 原則、異議の申立ての第1回期日は申立日から40日以内と決められていますが、第1回期日前の提出期限までに自分の言い分を書いた「答弁書」と、言い分を裏づける「証拠書類」を提出しなければなりません。遅くとも第2回の期日が終了するまでに提出を終える必要があります。
ただ、慣れない作業を自分で行うということになれば、労働審判委員会や相手方に主張が正確に伝わらない心配があります。
A氏 そんなにタイトに答弁書と証拠書類を用意できませんよ。
前田 確かに書類等の作成は大変で時間もかかります。しかし、大事なことは自分の主張を正確に伝えることです。
労働審判手続を申し立てられた数々の経営者から相談を受けましたが、その多くが自分の価値観でものを考え「実際にはこうだ」「申立てをした従業員本人が知っている」と言います。
また、労働法はもともと労働者保護の観点で制定されています。
主張を正確に伝えるといっても、自分の生の声をわかりやすく伝えるということとは限りません。常識も人それぞれです。労働審判委員会が常識として扱う枠組みの中で表現していかなければ、かえって有害となりかねません。
労働関係紛争については、法律は労働者に有利であり、裁判所も、経営者からすると労働者寄りとしか思えない価値観を基準とした判断を下すのです。労働審判手続が、労働紛争が労働者の生活をかけた紛争であるとの認識からスタートしている制度であることを思い起こせば、ご理解いただけるかと思います。
労働法の分野では労働者側の慎重な意思の確認が求められ、事実関係・意思の確定性・確実性が重要となり、書面化が重視されます。つまり、経営者の考える道理は通用しません。それに気づかずに突き進めば、予想外の結果になります。
A氏 一体、どうしたらよいのでしょうか。
前田 自分の価値観にとらわれず、労働審判委員会がどのように解決しようとしているのかを観察し、事を運ぶことです。労働法に関する十分な知識や民事訴訟についての経験を有した弁護士に頼るほかないでしょう。
その場合、言いたいことばかりに囚われず、不利な点を十分に拾い上げて、原則として、3回以内の期日において、審理を集結しなければならないとして、紛争の迅速で集中的な解決を図ることを旨としている労働審判手続を、いかに有利に活用していくかを突き詰めて考えてながら、作戦を練っていかなければなりません。そこまで想定に入れて対応できる弁護士に依頼する必要がありますね。
全てがそうだというわけではありませんが、多くの場合、労働審判手続を申し立てられた経営者は、調停成立で事件を終了させるのが賢明な場合が多いようです。
労働審判委員会は労働審判で相当な事項を定めることできるとはいっても、おのずと制約があり、経営者にとって相当な内容とは限らないのです。
労働審判に限らず、労働事件に巻き込まれた場合にすべきことは、その場をどうしのぐかということに加え、今後同じ問題が発生しないようにどうすべきかを考えていかなければならないのです。
企業側のあるべきスタンス・心構え(必須)はこちら
企業側の対応の実際(必須)はこちら
労働問題全般についてはこちら
労働問題に対するセカンドオピニオンはこちら
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。