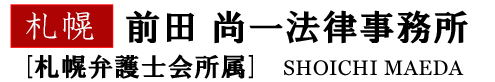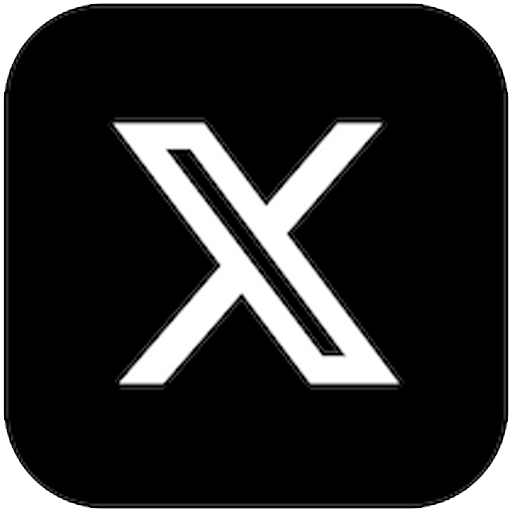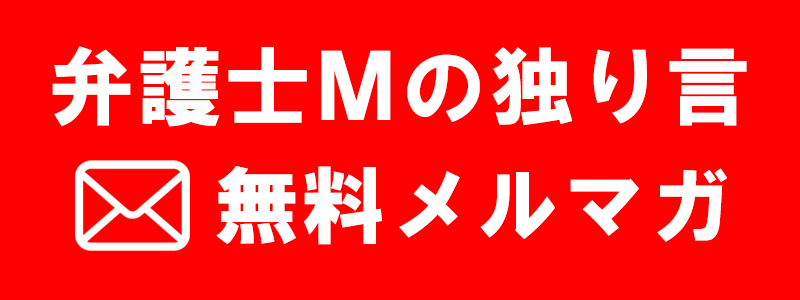団体交渉の主体
憲法は、その28条におきまして、勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体交渉をする権利を保障しています。 そうしますと、憲法上は、労働者が団結した団体であれば、団体交渉の主体として認められることとなります。
しかし、労組法上の権利を保障されるためには、労組法上の労働組合である必要があります。
労組法におきましては、以下のような要件が規定されています。
労組法は、その2条本文で、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体を労働組合と定めていますので、これを満たすためには、労働者が主体となること、自主性があること、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすること、組織する団体またはその連合団体であること、が必要となります。
また、2条但書におきまして、使用者の利益代表者の加入を認めないこと、経理上の援助を受けないことが要件として規定されています。
労組法5条2項におきましては、5条2項に規定されている規約の必要的記載事項の要件を満たすことが要件として規定されています。
以上のすべてを満たしているものを法適合組合といい、法適合組合でなければ労組法上の団体交渉の主体として、保護されないことになります。
また、主体となりうる使用者は、使用者自身または使用者団体となります。
使用者には、労働者と労働契約を締結するものは当然含まれますが、これに限定されるものではありません。
具体的には、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、労組法上の使用者に当たる、と判断されています(朝日放送事件 最判平成7年2月28日)。
また、請負における受け入れ企業であっても、下請企業が全く形骸化しており、受け入れ企業が自己の労働者のように取扱い、賃金も実質的に決定して支払っていたという事案において、受け入れ企業が使用者の地位にあると判断したものもあります(阪神観光事件 最判昭和62年2月26日)。
さらには子会社と親会社との関係につきましても、子会社の経営を支配下に置いているなどの諸般の事情により判断されますが、基本的には同様の考え方が採用されていると考えられます。
裁判所の判断には、子会社の持株会社が管理規定で子会社の人事・賃金については親会社の承諾が必要である旨の規定が存在した事案におきまして、親会社が経営戦略的観点から子会社に対して行う管理・監督の域を超えるものではないとして、支配株主としての地位を超えて、雇用契約の当事者である子会社がその労働者の基本的な労働条件等を直接支配、決定するのと同視しうる程度に具体的に支配力、決定力を有していることはできない、と判断したものがあります(ブライト証券ほか事件 東京地判平成17年12月7日)。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。