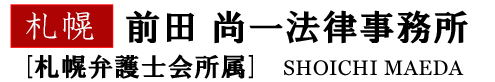残業が減り,実情に合わなくなった固定残業手当(定額残業代)の合意減額の効力に関する裁判例
Contents

会社が,固定残業手当を引き下げる内容の給与改定を書面により通知し,従業員から,会社から同書面の承諾書欄に応諾する旨の内容の署名押印を得,さらに給与改定同意書への署名押印を得て,改訂後の手当額により賃金を支払うこととしたが,従業員が,この労働条件変更の効力を争ったところ,従業員がこの合意の合意書等に承諾の署名押印をしていたとしても,およそ当該行為が従業員の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したとはたやすく認められず,労働条件変更が有効であるとみることはできないとされた事例(その他の興味深い争点は,「2 争点」をご確認ください。)
(東京地裁令和2年9月25日判決)
1 事案
従業員が会社に対し,次のことを求めた。
(1)会社から,懲戒処分として社屋への立入りを禁止されたほか,その後,懲戒解雇をされたところ,これら懲戒処分はいずれも無効であるなどと主張して,会社に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と,雇用契約に基づき,判決確定の日まで,毎月給料日限り,月例賃金額及びこれらに対する年6分の割合による遅延損害金の支払
(2)時間外・深夜・休日労働に係る未払賃金があると主張して,雇用契約に基づき,その額及び年6分の割合による遅延損害金の支払
(3)労働基準法114条に基づく付加金及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払
(4)法律上の原因なく,金銭を被告代表者によって被告に収奪されたなどとして,不当利得(民法703条)に基づき,利得金の額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
(5)会社代表者より暴行や暴言を受けたほか,④のとおり故なく金銭を収奪され,さらには違法な時間外労働を命じられたり,違法な懲戒処分・労働条件の切下げをされたりしたことが不法行為を構成するとして,会社法350条に基づき,損害金及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払
(6)会社が,従業員の所有に係るパソコンを不法に占有しているとして,所有権に基づき,その返還
2 争点
(1)本件出勤停止処分の有効性
(2)本件懲戒解雇の有効性
(3)賃金請求の肯否
(4)割増賃金請求の肯否(労働時間,固定残業代)
(5)付加金請求の肯否
(6)不当利得返還請求の肯否
(7)損害賠償請求の肯否
(8)動産引渡請求の肯否(本件パソコンの占有権限の有無等
3 判決(特に,固定残業代の合意減額につき)
主文
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1
2 前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
3 争点及びこれに関する当事者の主張
第3 当裁判所の判断
………
5 争点(3)(賃金請求の肯否)について
(1)前記説示のとおり,原告は,平成29年4月1日こそ出社したものの,同日午後8時40分頃には職務から離脱し,以降,労務の提供を行っていないから,賃金請求をすることはできず(民法624条1項),ただ,同法536条2項に則り,当該不就労による労務提供義務の履行不能が被告の責めに帰すべき事由によるものと認められる場合に限り,当該賃金請求をすることができることとなる。
そこで,これを本件についてみると,原告は,被告より同月3日,本件出勤停止処分を受けたものであるところ,同処分は無効というべきものであり,同月4日に本件出勤停止処分が解除されるまでの間の労務提供義務の履行不能は,被告の責めに帰すべき事由によるものと認めるべきものであるから,原告は,当該期間の賃金請求をすることができるというべきである。
(2)もっとも,本件出勤停止処分が解除された後から原告が本件懲戒解雇を受けるまでの間,原告が負っていた労務提供義務の履行に客観的障害があったとは認められないところであって,その間の労務提供義務の履行不能は,被告の責めに帰すべき事由によるものと認めることはできないから,その間の賃金請求をすることはできないというべきである。他方,本件懲戒解雇は前記説示のとおり無効というべきところ,これによれば,原告が本件懲戒解雇を受けた日以降の労務提供義務の履行不能は,被告の責めに帰すべき事由によるものと認めるべきものであるから,原告は,その日以降の賃金請求をすることができるというべきである。
この点,原告は,本件出勤停止処分の解除以降も,被告より暴行・暴言を行わないなどの誓約書が提出されなかったのであるから,被告の責めに帰すべき事由がある旨主張するが,本件出勤停止処分の解除に伴い,受領拒絶解消措置がとられ,労務提供義務は客観的に履行可能な状況となったものといわざるを得ないから,前記判断は覆らない。原告は上記の誓約書の提出が必要であるなどとも主張するけれども,労務提供義務は客観的に履行可能な状況となったものである以上,そのように解すべき根拠は見出し難いし,この点を措いても,弁護士(被告代理人)が介入し,被告代表者により暴行・暴言などしない旨誓約していたことにも照らせば,やはり被告の責めに帰すべき事由があったとみることは困難であって,かかる主張は採用することができない。
(3)以上によれば,原告は,被告に対し,平成29年4月1日から同月4日まで月例賃金を日割りによって計算した額の賃金請求及び同年7月6日以降,本判決確定の日まで毎月月例賃金相当額の賃金請求をすることができると解すべきこととなる。
(4)ところで,被告は,平成29年3月1日,給与改定に関する同日付け書面の承諾書欄に原告の署名押印を得,さらに原告から同日付給与改定同意書にも原告の署名押印を得るなどして,同年4月1日より原告の労働条件の変更(本件労働条件変更)を行っているところ,原告はその効力を争っている。
よって検討するに,これら書面作成時,原告は,被告の従業員であったものであって,上記のような労働条件の変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても,一般に労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれていること等にも鑑みれば,当該行為をもって直ちにその旨の同意があったとみるのは相当でなく,当該行為の有無だけでなく,当該意思表示により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様等の諸事情に照らし,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,本件労働条件の変更の内容は,前記認定のとおり,定額で支払われていた時間外手当の内容を月7万5000円から5万円へと引き下げるものであって,手当だけでみると約33パーセント,基本給を含めた給与額でみても12パーセント削減するものである。本件労働条件の変更の内容は,時間外手当の部分だけの削減ではあるが,実際には原告に対して定額残業代を超える支払がされたことはなかったものであり,この点も踏まえると,時間外手当の削減とは言っても実質的には減給と異ならず,その不利益の程度は相応に大きい。しかも,被告は,原告がアシスタント・ディレクターとしての業務を行うことができないことから原告の希望を踏まえ,総務の仕事を行ってもらうこととなり,残業が見込まれなくなったことから就業規則による標準的な定額時間外手当の額である5万円に引き下げることとし,原告からもその旨の同意を得た旨主張するが,そもそも原告は,被告の上記主張にいうような職種の変更はなかった旨主張して上記被告の主張を否認しており,確かに,前記認定のとおり,原告が忌避されていた放送業者の関与する番組制作の担当を外れることこそあったものの,永続的に担当職種の変更がなされたと認めるべき証拠もなく,被告自身もこの点,上記合意前後で顕著な職務違いがあったともいえないかもしれないなどと指摘しているところでもある(被告第4準備書面9頁)。そうしてみると,前記定額時間外手当の削減は,労働実態の特段の変更がない中行われたものといわざるを得ない。加えて,被告が上記のような職種変更を行うに当たり,時間外手当の削減をしたい旨の説明を大なり小なり施したことを認めるに足りる証拠もない。かえって,原告は,時期こそ違えども被告代表者から暴行を受けていたほか,原告の怠業により多額の損害を生じたなどとして,本件書面1及び2のような多額な債務負担を求められ,月額の分割払いを求められていたものであって(なお,本件書面1及び2の効力については,後記6参照。),そのような事実もあった本件においては,原告が上記合意の合意書等に承諾の署名押印をしていたとしても,およそ当該行為が原告の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したとはたやすく認められず,本件労働条件変更が有効であるとみることはできない。
(5)以上によれば,原告は,月額22万5000円の月例賃金による賃金請求ができることになる。
そこで,これを踏まえて原告が請求できる賃金額について賃金規程6条に鑑み計算すると,平成29年4月1日から同月4日までの賃金として,下記計算式による以下の金額を請求することができるものと認められる。
(計算式)
22万5000円(月例賃金)÷20.5日(1か月平均所定労働日数。別紙5,月所定労働時間シートからすると,月平均所定労働時間164時間を所定労働時間8時間で除して得られる額となる。)×2日(上記期間内の休日でない日数)=2万1951円
また,同年7月6日以降,本判決確定の日まで毎月月額22万5000円の割合による賃金請求をすることができることとなる。
そこで,遅延損害金については商事法定利率年6分(ただし,令和2年4月以降の支払期日に係る月例賃金の遅延損害金については,平成29年法律第44号による改正後の民法所定の年3分)によりこれら請求を肯認すべきである。
なお,被告は,以上に対し,被告が本件出勤停止処分の解除以降,労務の提供を求めても応じようとしなかったことに照らせば,原告からは黙示の退職の意思表示があったとみるべきものであるなどという主張もするが,そのような意思表示がなされたとは認めるに足りず,その主張は採用できない。
………
10 以上によれば,……。
よって,主文のとおり判決する。なお,仮執行免脱宣言を付することは相当ではないから,これを付さない。
4 解説(特に,実務上の留意点)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。