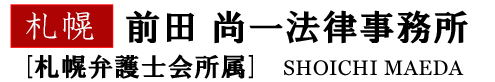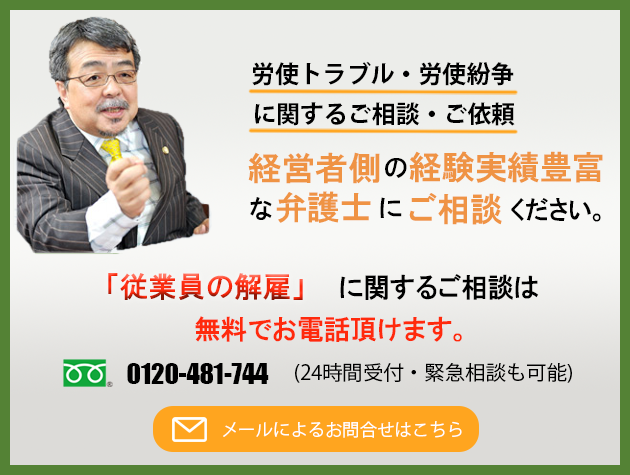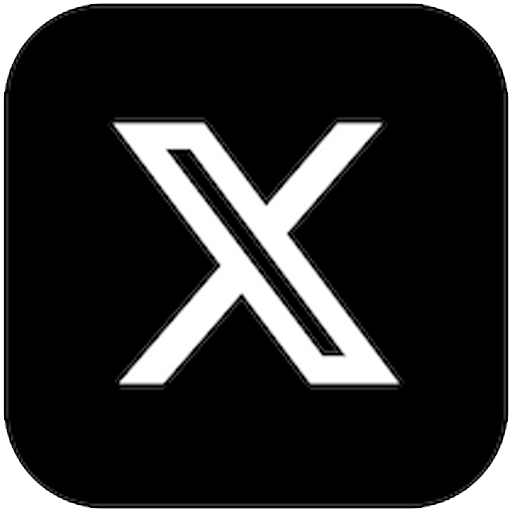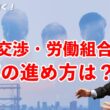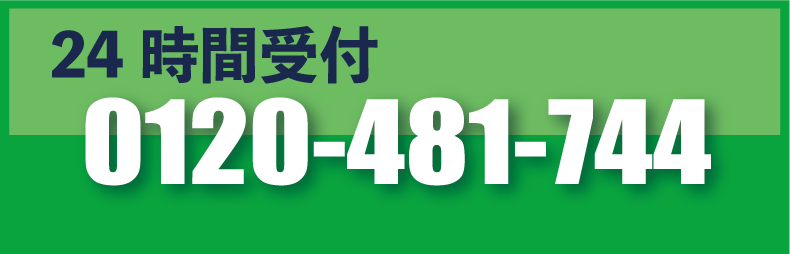ユニオン・ショップ協定:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
Contents
「労働組合対策・団体交渉・不当労働行為」の実際は
こちらをご覧ください。
ユニオン・ショップ制度とは
ユニオン・ショップ制度とは、労働組合が、使用者に対して、当該労働組合に加入しない労働者および当該組合の組合員ではなくなった労働者を解雇する義務を課すという、使用者との協定を定めている制度のことです。
そして、ユニオン・ショップ制度を定めている労働組合と使用者との間の書面化された合意をユニオン・ショップ協定といいます。
わが国では、過半数の労働組合において、このユニオン・ショップ制度を採用しています。
この点に関しまして、労働者に特定の労働組合への加入を強制している点、またユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力が問題となっています。
まず、労働組合への加入を強制している点に関してですが、一般的には、憲法28条におきましても、労働者は組合に加入する自由を保障されてはいますが、組合に加入しない自由までは保障されていないと考えられています。
しかし、労働者の組合選択の自由は、憲法28条の団結権の重要な内容となっています。
そうしますと、労働組合のへの加入の強制が、この組合選択の自由を侵害することは許されませんので、労働者が別の組合に加入している場合には、労働組合に加入しないことを理由として使用者の解雇義務を定める部分は、公序良俗違反(民法90条)として無効となるとされています(最高裁平成元年12月14日判決[三井倉庫港運事件])。
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇
次に、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇についてですが、裁判所は、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、協定によって使用者に解雇義務が発生している場合に限り、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができる、とし、有効なユニオン・ショップ協定に基づく解雇は権利濫用にあたらないとしています(最高裁昭和50年4月25日判決[日本食塩製造事件] )。
しかし、労働者が、労働組合から除名された後に、どの組合にも所属していない場合に、ユニオン・ショップ協定に基づいて解雇がなされたものの、その除名処分が法的に無効であった場合につきまして、裁判例は分かれていましたが、最高裁判所は、除名が無効である以上は、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇義務は生じていないため、他に解雇の客観的合理性および社会的相当性を基礎付ける特段の事情がない限り、解雇は権利濫用として無効となると判断しています(上記日本食塩製造事件判決)。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。