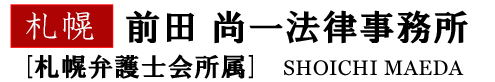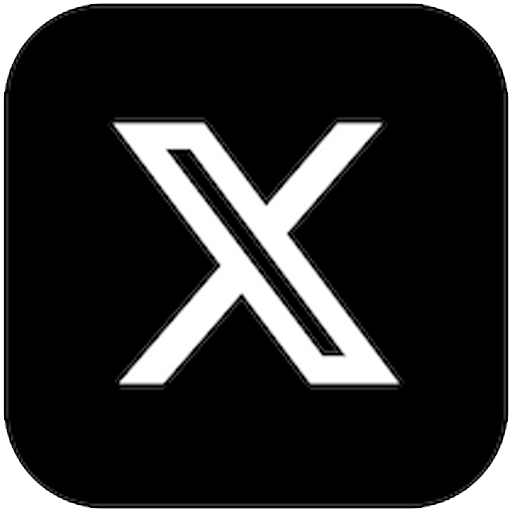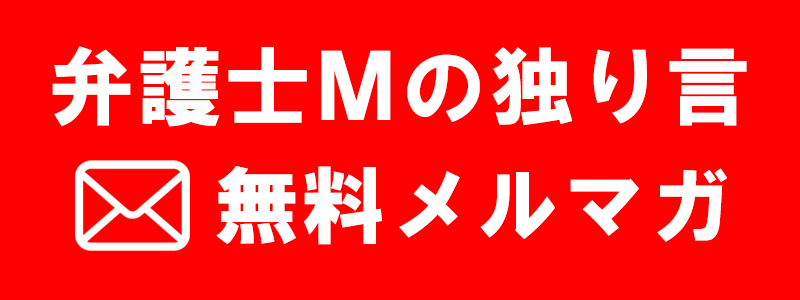労働組合と団体交渉・争議:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
Contents
「労働組合」・「団体交渉」対策全般については
こちらをご覧ください。
経営者と対等な交渉をするために,労働者は組織をつくります。これを労働組合といい,憲法や労働組合法にさまざまな規定が置かれています。
労働組合
労働組合の組合員の範囲については,さまざまなものがありますが,我が国で一般的なのは,企業別組合です。特定の企業または事務所に働く労働者を職種の別なく,組合員とするもので,終身雇用制と結びつくことで,労働組合の基盤を着実なものにしていました。
また,我が国の労働組合にはユニオン・ショップ制というものを採用していることが多いです。これは,労働組合に加入することを雇用の条件とし,労働組合を脱退したら解雇するという内容の,労働組合と経営者との間の合意です。これは労働組合の組織拡大という本質的な欲求を満たすことにつながるため,我が国で広く普及しました。
労働組合と団体交渉
多くの社員を抱えて肥大化した労働組合は,組合員の数を背景に,賃金,労働時間,休日,安全衛生,災害補償,教育訓練といった労働条件について,経営者に対し,交渉をしてくることがあります。もちろん,労働組合の言いなりになる必要はありませんが,労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒むと,「不当労働行為」とされるおそれがあります(労働組合法7条2号)。
不当労働行為があったと労働組合が考えた場合,労働組合は労働委員会に不当労働行為に対する審査の申立てをすることがありえます(労働組合法20条)。労働委員会が出した結論に対しては,中央労働委員会にさらに審査の申立てをすることができます(労働組合法27条の10)。中央労働委員会が救済命令を発したときは,経営者は救済命令の取消しの訴えを提起することも可能です(労働組合法27条の19第1項)。
争議
労働組合は交渉がうまくいかない場合,実力行使として,ストライキなどの実力行使に出ることもあります。労働組合法で一定程度認められてはいますが(労働組合法1条2項本文),暴力行為に及ぶことは絶対に許されません(労働組合法1条2項但し書き)。
労働者の定義
労働者とは、労働基準法、労働契約法、労働組合法など、多種の法律で使用されている言葉です。
そこで、労組法上の労働者とは、いかなるものを指すのかが問題となります。
労組法3条は、労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者、と規定しています。
具体的には、最高裁判所は、不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていること、契約内容が一方的に決定されていること、基本的に仕事の依頼に応じる関係にあること、労務の対価として報酬が支払われていること、指揮監督を受けていること、場所的時間的拘束を受けていること、などを総合的に考慮して判断しています。
この最高裁判所の基準は、基本的には、使用従属性を重視しつつ、労基法上の労働者の判断基準よりも緩やかな基準を立てていると考えられています。 具体的には、労基法上の労働者では、仕事の諾否の自由がないことを裁判所は求めていると考えられますが、労組法上の労働者については、基本的に仕事の依頼に応じる関係があればよいとしていると考えられます(新国立劇場運営財団事件 最判平成23年4月12日)。
労働組合の主体
また、労組法において、労働組合と認められる団体であるためには、労働者が主体となって組織するものでなければならない、とされています。 この定義は、労働組合による団体交渉を助成するために定められた労働組合法の保護を及ぼすべき者は誰かという観点から定められています。
ですから、労働基準法や労働契約法とは観点が異なっています。
労組法の団体交渉の保護を及ぼすべき者としましては、労働契約下における労務者や職員を想定した上で、これに準ずる収入によって生活する者にまで拡大した定義づけと考えられています。
団体交渉の保護を及ぼす必要性と適切性
つまりは、労働契約下の労働関係に類似した労働関係である、請負や委任その他の契約による労務提供関係によって賃金や給料に準ずる報酬を得る者であっても、団体交渉の保護を及ぼす必要性と適切性が認められれば、労組法上の労働者と認めようとしたものと理解されています。
さらに、労組法は、職業別労働組合など、労務供給者が特定企業との労務供給関係に入る前に加入し、同関係が切れても加入し続ける超企業的労働組合の存在を前提として立法されていますので、賃金、給料その他これに準ずる収入を現在得ていなくても、それを得て生活する職業にある者、つまりは、失業者も含まれます。
労働組合の成り立ち
労働組合は、労組法2条本文、但書の要件、および、労組法5条2項の要件を満たすと、憲法および労組法上のすべての保護を受けることができます。
労組法2条本文の要件とは、労働者が主体となること、自主性があること、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすること、組織する団体またはその連合団体であること、であり、但書の要件とは、使用者の利益代表者の加入を認めないこと、経理上の援助を受けないことです。
労働組合の該当性
労組法5条2項の要件とは、5条2項に規定されている規約の必要的記載事項の要件を満たすことです。
上記要件を全て満たす労働組合を法適合組合といい、労組法2条本文、但書の要件を満たすものの、労組法5条2項の要件を満たさないものを規約不備組合、労組法2条本文の要件を満たすものの但書1号2号のいずれかまたは双方の要件を満たさないものを自主性不備組合といいます。
この中で、一番問題となりやすいのは、2条本文における自主性の要件と考えられています。
②自主性の要件について これは、労働者が自ら組織し、使用者の支配から独立した組織であることを要求するものです。 労組法2条但書では、使用者の利益代表の参加を許すもの、と、使用者から経費援助を受けているものについては、2条本文にいう労働組合には該当しないとされています。
この点に関しまして、裁判例では、同条但書に該当しても、実質的に自主性を有しているといえれば、労働協約締結能力を有すると、実質的に自主性の有無を判断すべきとしたものもありますが(高岳製作所事件 東京地決昭和25年12月23日)、近年におきましては、実質的に見て団体の自主性を阻害していない場合には、同条但書に該当しないと判断するものもでています。
具体的には、会社役員が参加する労働者団体について、当該役員が実質的に取締役としての職務を担っていたとはいえないと判断し、同条但書1号該当性を否定し、労働協約締結能力を認めました(伊藤製菓事件 東京地判平成12年2月7日)。 つまり、同条但書に該当すれば法適合組合とはなり得ないと捉え、その上で、同条但書該当性を限定的に判断していると考えられています。
団体的労使関係とは
団体的労使関係とは、労働者の労働関係上の諸利益を代表する労働者団体の組織と運営、労働者団体と使用者又は使用者団体間の協議・交渉を中心とした諸関係のことです。
そして、労働者の労働関係上の諸利益を代表する労働者団体は、現行法上は労働組合となります。
労働組合とは、労働組合法によれば、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます(労働組合法2条本文)。
ですので、使用者の利益代表者の参加を許す労働組合や、使用者から経理上の援助を受ける組合等につきましては、労働組合法上の労働組合とはいえないと考えられています(労働組合法2条各号)。さらに、労働組合は、労働委員会に証拠を提出して、2条及び5条2項(規約の必要的記載事項)に適合することを立証しなければ、労働組合法上の法的保護を享受できないこととなります。
労働組合法の目的
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させる、ことを目的としています。
労働組合の形態と種類に関しましては、組合員の範囲による種別として、職業別組合、産業別組合、一般労組、企業別組合、地域労組などがあります。
そして、日本におきましては、約9割程度が、企業別組合となっています。
企業別組合
企業別組合とは、特定の企業又は事業所に働く労働者を、職種の区別なく組織した労働組合のことです。
そして、これらの企業別組合の多くが、その上部団体として産業別の組織を有しています。
企業別組合は、団体交渉により、組合員の労働条件を利するという労使対抗団体として役割と、企業の繁栄や従業員の福利のために企業経営に関与する労使協力団体としての役割とを持っていると考えられます。
労使対抗団体という面をみますと、労使の利害対立があることを前提として、自発的結社性や独立性が要請されると考えられていますが、労使協力団体としての面をみますと、従業員は当然に加入し、労使協調性等が要請されることにもなります。
このように、企業別組合は、両面を併せ持つという性質がありますが、労働組合法におきましては、労働組合を団体交渉の主体となり得るように、労使対抗団体の側面を捉えて法的保護を与えています。
労働組合は任意団体
労働法の前提とする労働組合は、労働者の自発的結合に基づく結社であり、任意団体ですから、労働者が、組合員たる地位を取得するためには、加入行為が必要となります。
組合は、組合員資格につきましては、組合契約や労働協約で決定できますが、組合民主主義に反するような資格要件を定めたり、特定の人種、宗教、性別、門地等を理由としたりしますと、その定めは無効となります。
労働組合脱退の自由性
そして、組合員には、労働組合脱退の自由が認められています。 その根拠としましては、憲法28条の解釈として認められるとするものや、労働組合が労働者の自発的結社であることから性質上当然のものと考えるものなどが存在します。 裁判所は、その根拠は明らかにしていませんが、労働者に、労働組合脱退の自由を認めています(最高裁昭和50年11月28日判決[国労広島地本事件])。
このように、労働者には、脱退の自由が認められていますから、組合が脱退の要件として組合の承認を必要としても無効となりますし、争議中の脱退は認められないとの規定も無効となります(東京高判昭和61年12月17日判決[日本鋼管鶴見製作所事件]、 札幌地裁昭和26年2月27日判決[浅野雨龍炭鉱労組事件])。 ですので、労働者は、脱退届等を提出すれば、有効に労働組合を脱退したこととなります(最高裁平成元年12月21日判決[日本鋼管事件])。
ユニオン・ショップ協定の存在
ただし、労働組合が、労働者に対して、脱退に際して一定の手続きを要求することや、ある程度の予告期間を要求することは、脱退の自由の制限とならないのであれば許されると考えられています。 このように、労働者には、労働組合を脱退する自由が認められていますが、労働組合が、組合員の脱退を防止する手段としては、ユニオン・ショップ協定が存在し、これにつきましては、一定限度で有効性が認められています。
また、労働者と使用者の間で、特定の労働組合に所属し続ける旨の合意がなされていた事案について、労働者がこの合意に反して組合から脱退した場合には、使用者との間で当該合意についての債務不履行責任の問題が生ずる場合があるとした最高裁判所の判断もあります(最判平成19年2月2日[東芝事件])。
組合員は,労働組合を脱退する自由を有しているということは,法律家の間では,常識の事柄であるといってよいと思います。
ところが,労働組合を脱退する自由が学者の議論となると,憲法論などの論争となる傾向があります。
しかし,現実の判例・裁判例を確認すると,出来事の実態は,労働組合が徴収する組合費の納付に疑問を持った組合員が,流れに任せて加入した労働組合を脱退したところ,労働組合側が争いを挑んできたといった事例が,大勢であるように思われます(中には,会社側の,第二組合結成に起因する事案も見られます。)。
また,一旦トラブル化すると,労働組合側は,いろいろ主張をしてくるようですが,多くは,反論のための主張にすぎないようです。
ここでは,以下に,実際的解決を図る上で,まずは組合員の脱退の自由の法的根拠に触れ,脱退の自由を制限する組合規約が原則無効であり,労働組合側がする組合員脱退に対する無効の主張もまた、原則的に無効であること,そして,この種のトラブルについて,当事務所がお手伝いできる内容をご説明いたします(なお,一定限度で有効性が認められており,労働組合が組合員の脱退を防止する手段となるユニオン・ショップ協定については,ここでは説明しません。)。
組合員の脱退の自由の法的根拠
判例では,組合員の脱退の自由の法的根拠を明示されていません。
しかし,最高裁は,組合員が,労働組合に服従し,ある程度の人格的な支配を及ぼされる立場に置かれ,個人としての自由を強度に制約されることとなることを容認する労働組合の統制権の法的根拠については,「労働組合の組合員は,組合がその目的を達成するために団体活動に参加することを予定してこれに加入するものであり,また,これから脱退する自由をも認められているのであるから,右目的に即した合理歴な範囲において組合の統制に服すべきことは,当然である。」とか(「国労広島地本組合費請求事件」最高裁昭50・11・28),「労働組合は,組合員に対する統制権の保持を法律上認められ,組合員はこれに服し,組合の決定した活動に加わり,組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが,それは,組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。」(「東芝組合二重加入事件」最高裁平19・2・2判決」)などとしています。
そこで,最高裁は,従業員の強制加入組織ではなく,労働者の自発的結合に基づく結社であるので,組合員の脱退の自由は,労働者の加入と同様に,団体の性質上当然の論理的帰結であるとする考え方を前提としているであるといわれています(後掲「総評全金協和精工支部事件」もこの前提は同旨です。)。
脱退の自由を制限する組合規約が無効とされる場合
そして,下級審の裁判例は,組合員の脱退に組合の機関の承認を要するものとする組合規約は脱退の自由を不当に制限するものとして無効であるとするのがほとんどのようです「日本鋼管鶴見製作所事件」東京高裁昭和61・12・27判決,「浅野宇龍炭鉱労組事件」札幌地裁昭26・2・27判決)。
また,争議中の脱退に関しては,権利の濫用であり効力を生じないという主張がしばしばされますが,これが容れられ裁判例はほとんどないとのことです。
脱退の自由を制限する組合規約が有効とされる場合
もっとも,裁判例を見ると,一定の手続をもって脱退の効力発生要件とすることは,それが実質的に脱退の自由を制限するものでない限り,合理的なものとして許され,有効であると解すべきであるとしています。
脱退の効力発生を中央執行委員会の確認又は承認の議決に係らしめるものではなく,を脱退の意思表示は中央執行委員会がこの意思を確認したときに効力を生ずる旨の組合規約は,違法とはいえないとしています。(「全逓神戸港支部事件」神戸地裁昭63・12・23判決)。
さらには,裁判例の中には,組合員の脱退が,もっぱら支部の団結を乱し会社に利益を与えるような目的・態様をもってなされたとみられても仕方のないものである場合には,権利の濫用として無効というべきであるとするものがあります(「総評全金協和精工支部事件」大阪地裁昭55・6・21決定)。
しかしながら,稀有な例というべきでしょう。
近時の最高裁は,従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において,この合意のうち,従業員に労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は,公序良俗に反し無効であるとしており(前掲「東芝組合二重加入事件」判決),ともかくも組合員の脱退を無効とした裁判例には問題があると考えれます。もっとも,この裁判例のような事案では,組合員に不法行為に基づく損害賠償責任が検討される余地はあるでしょう。
当事務所のできるお手伝い
当事務所は,労働問題については,使用者での対応のみを取扱分野としておりますが,そのため,「労働組合対策・団体交渉・不当労働行為」という分野で,対労働組合,対上部団体とすることが多く,労働組合からの脱退を希望される方々の要望にも応じれることになります。
もし,労働組合からの脱退について困っている方がおられたら,まずはご相談に応じたいと思いますので,お電話ください。
「経営者の常識は危険!」はこちら
ートラブル・紛争に直面した場合の経営者・管理者のスタンス
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。