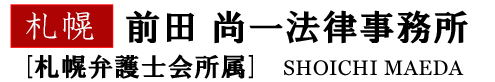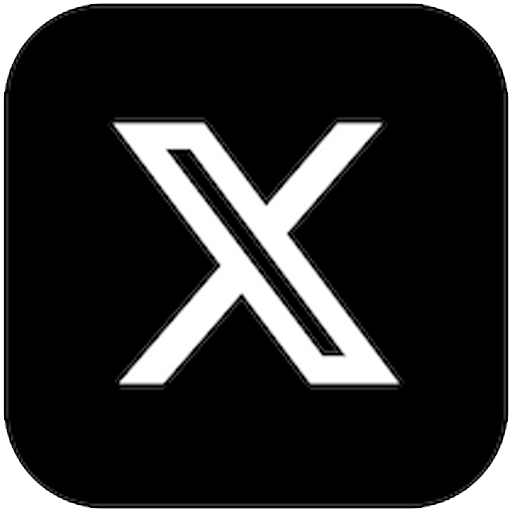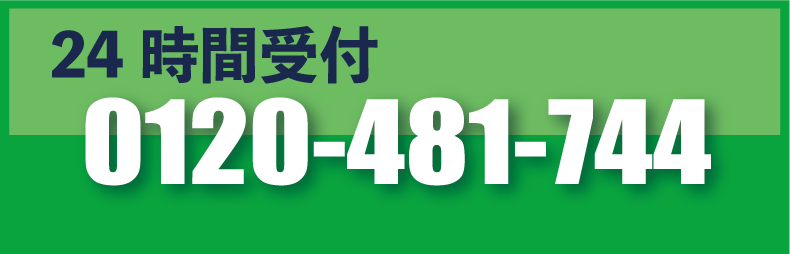最高裁で札幌高裁の不当判決を覆した事例:内部告発者に対する訴え提起の正当性が認められた判決
Contents
最高裁判所で、不当な札幌高等裁判所を破棄してもらった事例をご紹介いたします。
特養ホームである社会福祉法人の代理人として担当した事件で、札幌高裁が当方を敗訴させたことから、最高裁に上告受理を申し立てました。
最高裁は、上告を受理し、札幌高裁判決を破棄したうえ,差し戻しました。
1 始めに、この事例の「お客様の声」をご紹介いたします。
社会福祉法人・施設長・女性
ある日、思いがけない案件が発生し、前田先生の事務所にお伺いしました。その時に、「依頼者と協働作業でやらなければ良い成果は得られない」と先生がおっしゃったことを覚えています。どんな些細なこともお伝えしなければ、現場の状況は分からないと思い、私は出来る限りの情報をお届けしようと思いました。
先生への電話、法廷でお留守の時はメール、FAX等で連絡を入れました。色々な方法で連絡を入れましたが、先生は何時も必ず、それに対する返事を下さいました。又、打ち合わせの際も、案件以外の雑談の中からも、先生は何かを感じ取って下さり、案件へ結びつけてくださいました。私の話の中から、何かを汲み取る感性には、いつも感心しました。素人の私の見る観点と、違う事を痛感しました。
初めての記者会見や、法廷への出廷、不安と緊張の中、先生に助けて頂き、何とか乗り切る事が出来たと思います。色々な困難や様々な事柄に、逃げ出したくなったこともありました。でも「協働作業」の言葉を思い出し、何とか頑張ることができました。以前の職場でも、弁護士に依頼した案件がありましたが「協働作業」にはならず、質問にも答えが得られず、苦労したことがありました。
前田先生への、私からのラブレター(連絡用のFAX)綴りは、莫大な量となって残っています。お忙しい中、それを全て見て下さり、回答を頂いた事に感謝しています。
2 事例は、次のとおりです。
【判示事項】
施設入所者に対する虐待行為が行われている旨の記事が新聞に掲載されたことに関し、複数の目撃供述等が存在することを認識していたものの、他の事情から虐待行為はなかったとして、同施設を設置経営する法人が新聞への情報提供者である職員らに対してした損害賠償請求訴訟の提起が違法な行為とはいえないとされた事例
平成21年10月23日
最高裁判所第二小法廷
謝罪広告等請求本訴,慰謝料請求反訴事件
平成20年(受)第1427号
[公刊物] 最高裁判所裁判集民事232号127頁
裁判所時報1494号303頁
判例タイムズ1313号115頁
判例時報2063号6頁
【判決要旨】
特別養護老人ホームの入所者に対して虐待行為が行われている旨の新聞記事が同施設の職員からの情報提供等を端緒として掲載されたことにつき,同施設を設置経営する法人が,虐待行為につき複数の目撃供述等が存在していたにもかかわらず,虐待行為はなく上記の情報は虚偽であるとして同職員に対し損害賠償請求訴訟を提起した場合であっても,(1)虐待行為をしたとされる職員が一貫してこれを否認していたこと,(2)情報提供者である職員の目撃状況についての報告内容につき同施設の施設長は矛盾点があると感じていたこと,(3)入所者の身体に暴行のこん跡があったとの確たる記録もなく,後に公表された市の調査結果においても個別の虐待事例については証拠等により特定するには至らなかったとされたことなど判示の事実関係の下においては,同訴訟の提起は違法な行為とはいえない。
3 地元の北海道新聞が平成21年10月23日夕刊で「特養ホーム内部告発訴訟 高裁判決を破棄」という見出しで記事を掲載したほか、日刊全国紙、TVニュースで報道されました。
この事件は、最高裁判所のHP(裁判所ウェブサイト)・「裁判所時報」1494号303頁のほか、二大判例雑誌である『判例タイムズ』1313号(平成22年2月15日号)115頁、『判例時報』2063号(平成22年3月1日号)6頁に登載されました。
札幌高裁判決の判断は,後掲【上告受理申立理由】で述べるとおり,裁判制度の長年の歩みの中で形成された,制殿原則として正当な行為である訴えの提起を敢えて不法行為を構成するかどうかを判断するにあたっては慎重な配慮をしなければならないという最高裁の考え方を無視するものであることに加え,最後の救済の砦でもある訴訟の現場における,裁判所,裁判官の在り方にも大きな問題があるものでした。
判例雑誌である判例時報、判例タイムズは、コメントの中で、「原審の判断は、提訴者に高度の調査、検討義務を課すもので裁判制度の自由な利用の確保という観点からは、疑問があるものといわざるを得ない。」などと当方を敗訴させた札幌高裁判決に対して批判的な論評をしています。
この判例雑誌のコメントは、匿名ですが、裁判官が書いているといわれています(特に、最高裁の判決の場合は、担当した調査官が書いているといわれています。)。コメントの中では批判的論評はされないのが通常であり(せいぜい「……いる点にやや問題があろう。」という指摘にとどまる。)、敢えて上記のように苦言ともいえる批判的論評がされたことは、札幌高裁の判決がいかにひどいものであったかを明確に裏付けるものです。
ところで,新聞報道によると,被上告人が,札幌市内で記者会見し,同席した代理人弁護士が,「最高裁判決は過去の判例を機械的に当てはめたもの。提訴の適法性を個別具体的に判断してもらいたかった」と話したとのことです(平成21年10月24日北海道新聞朝刊)。しかし,最高裁の判決が,個別具体的に判断していることは明らかで、同代理人が何を言おうとしているのか,全く理解できないところです。
【参照法条】
民法709条,民訴法第2編第1章
【参 考】
[上告審として受理された部分に関する申立ての理由中,重要と認められた部分]
第3 反訴請求について
第一審判決中の相手方Y1ら敗訴部分を敢えて取り消して,不法行為の成立を認めた原審の判断には,最高裁判所の判断がない解釈問題について,誤った法令解釈をした違法があることに加え,最高裁判所判例に違反し,法令の解釈を誤った違法がある。その理由は,次のとおりである。
1 原審が,申立人による本訴提起行為を訴えの提起が違法な行為として違法であると判断した点について
(1) 原審は,《控訴人による本訴提起行為((1)のアの(ク)及び(2)のアの(カ))は,被控訴人Y1及び同Y1の情報提供行為が虚偽のものであることを前提とするものであるところ,前記認定のとおり,その情報提供行為はいずれも主たる部分において真実なものと認められ,また,前記認定したところによれば,控訴人は,Bからのより詳しい事情聴取等当然行うべき調査を行わず,Bの虐待に関する複数の供述等を合理的な根拠もなく虚偽と決めつけて,本訴提起に及んでおり,本訴は,権利の存在につきわずかな調査をしさえすれば理由のないことを知り得たにもかかわらずこれを怠って提起されたものということができ,違法性が認められる。》と判断した。
(2) しかしながら,最高裁判所判例は,訴えの提起が不法行為となる場合の要件について,《民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が,事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。》と判示しているところ,その前提として,《法的紛争の当事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求めうることは,法治国家の根幹にかかわる重要な事柄であるから,裁判を受ける権利は最大限尊重されなければならず,不法行為の成否を判断するにあたっては,いやしくも裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう慎重な配慮が必要とされる》と述べ,また,《けだし,訴えを提起する際に,提訴者において,自己の主張しようとする権利等の事実的,法律的根拠につき,高度の調査,検討が要請されるものと解するならば,裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。》と理由付けとしており(最高裁判所第三小法廷昭和63年1月26日判決・民集42巻1号1頁),訴えの提起が違法な行為にあたる場合を制限的に解していることは明らかである。
現に,上記判決は,前訴が,相手方を土地の売主,土地の測量の依頼者であると誤信して提起されたものであるところ,真の売主,依頼者を客観的方法で一義的に確定するこが可能である事案に対するものであるが,それでも,《・・・・・・,いまだ通常人であれば容易に知りえたともいえないので,・・・・・・更に事実を確認しなかったからといって,上告人のした前訴の提起が裁判制殿趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとはいえず・・・・・・》などと判断して,不法行為の成立を否定して,請求を棄却した。
これに対し,本件は,申立人としては,客観的痕跡がなく,目撃供述と被告発者の供述が相対立している状況では,申立人としては,少なくとも現場で全般的,個別的な諸々の関わりを持つものとしては,軽視できない個人面談での供述内容,作成メモ,投書の記載内容に接し,これ以上の調査を進めたとしても,原審の判断と同一の結論を真実と確定するなど到底できない状況にあった。
前記第2の2(4)のとおり,存在する物的,人的資料にほとんど無制限に直接接することができ,時間的な制約もなく,調査を実施した札幌市でさえ,《個別の具体的事例について,行為者やその行為を証拠等により特定するには至らなかった》という結果を出さざるを得かったのである。
そうであるにもかかわらず,申立人の訴え提起を,《・・・・・・権利の存在につきわずかな調査をしさえすれば理由のないことを知り得た》などと説示するのは,申立人が,突如起こった虐待疑惑の中で右往左往しながら,素人で稚拙ながらも何とか真実を確認しようと努力してきたことに一顧だにせずに無視するものにほかならず,独断的な判断というほかない。
高等裁判所民事部が2箇部しかない高裁管内においては,上記のような判断が,裁判官,殊に裁判長の考え・個性によって安易にされれば,管内での控訴提起が萎縮抑制され,裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となりかねない。
なお,原審で取り調べられたA施設長の証言中には,確かに思い込み甚だしいと評価されてもやむを得ないものもあるが,それは,事実そのものではなく,判断過程,意見に関わる部分であって,原判決中に,敢えてA施設長の供述を基に縷々事実認定をする一項を設けて,申立人に不利な結論を導く材料とするまでもないと考えられ,申立人の立場としては,A施設長の証言態度に対する過剰反応と思わざるを得ない。
(3) いずれにしても,以上のとおり,原審の前記判断には,前記最高裁判例に違反して不法行為の成立を認めるものであって,法令の解釈適用を誤った違法があることは明らかである。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。