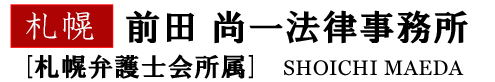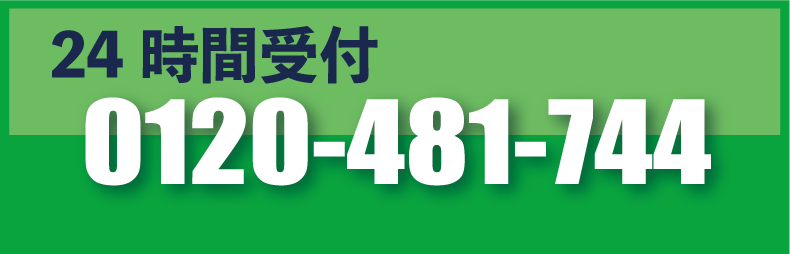労務問題法律・総集編の記事一覧
2024/11/18
弁護士が消える・弁護士が消される
ある社長A氏と弁護士と人工知能(AI)について語りました。 A氏 10~20年以内にロボットに取って代わられそうな職種として「弁護士」が挙げられています。 前田 アメリカの報道機関CNNでは「訴訟以外の弁護士の仕事は、ま 続きへ
2024/11/17
嫌なら代えろ!顧問弁護士の選び方・付き合い方
新進気鋭のA社長と当事務所の顧問先でA社長の先輩であるB会長の会話を紹介します。 経営者のパートナーである「顧問弁護士」がキーワードです。 A社長 顧問弁護士をお願いしたいと思うのですが、どのような点に注意して選ぶべきで 続きへ
2024/11/16
派遣労働者と黙示の労働契約
現在では、業務の効率化のために、労働者を自社で直接雇用するだけでなく、企業外の労働者を労働力として利用しています。その形態の1つに労働者派遣があります。 本来、職安法により労働者供給事業は違法とされますが、労働者派 続きへ
2024/11/14
弁護士による高齢者雇用安定法改正の解説
1 「高年齢者雇用安定法」とは? 令和3年4月より、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が施行されました。 高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少するなか、経済社会の活力を維持 続きへ
2024/11/12
契約の締結過程(募集)
わが国では、職業選択の自由(憲法22条1項)、財産権(憲法29条)を根拠として、使用者に採用の自由が認められています。 そして、採用の自由には、募集方法の自由、選択の自由、調査の自由、契約締結の自由があると考えられ 続きへ
2024/11/11
労働時間の始点・終点
労働基準法89条1号は、始業および終業の時刻を、就業規則の必要的記載事項として、規定しています。 就業規則は、労働契約法7条により、労働契約の内容となりますから、労働者は始業時刻から終業時刻までの就労義務を負ってい 続きへ
2024/10/31
労働契約の締結過程(採用選考)
使用者は、労働契約を締結するに際して、基本的には採用の自由を有します。しかしながら、法律や裁判所の判例により種々の制限がなされています。 これを採用における労働者選択についてみれば、採用選考過程について、裁判所は 続きへ
2024/10/30
労働契約の成立(採用内定)
わが国では、一般には、採用内定から就労に至るまでかなりの期間を有することが多いです。 そこで、採用内定と労働契約の成立との関係がいかなるものかが問題となります。 この点に関しまして、採用内定の法的性質として 続きへ