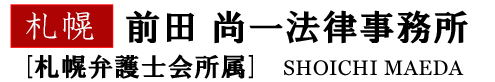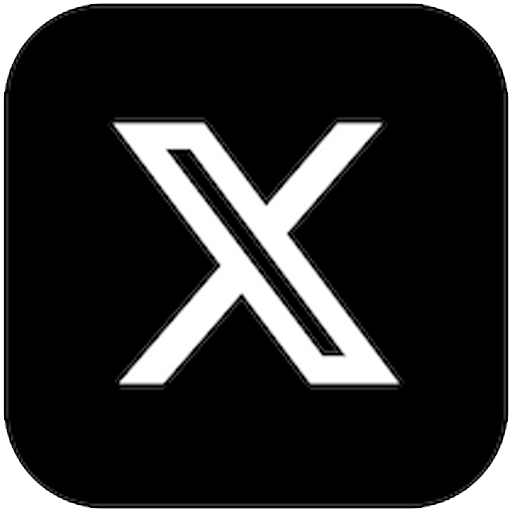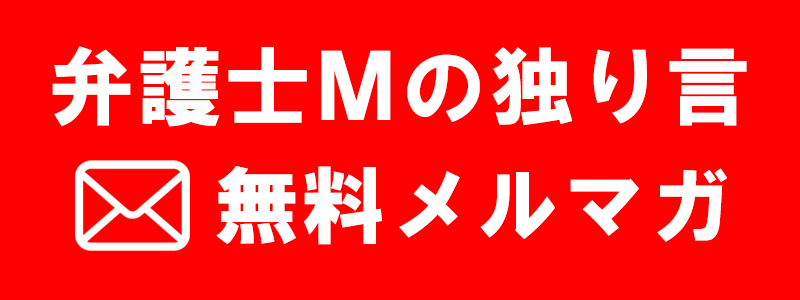休職制度・休職期間の満了と退職・解雇について:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
休職とは(概要)?
休職とは、従業員について、労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者が、その従業員に対して労働契約関係そのものは維持させながら、労務への従事を免除または禁止することです。
休職制度は、企業においては法令に基づくものでありません。ですから、就業規則や労働協約により定められるものとなりますが、使用者と労働者の合意でなされることもあります。この点、公務員につきましては、法令の定めがあります。
休職には、一般的には、業務外の傷病により長期欠勤する場合である傷病休職、傷病以外の私的な事故を理由とする事故欠勤休職、刑事事件に起訴された場合の起訴休職、労働者の出向の際の出向休職、自己都合による長期欠勤の場合の自己都合休職などがあります。
これらの休職制度につき、裁判所は、その目的、機能、合理性、労働者が受ける不利益の内容等を勘案して、就業規則の合理的解釈をするという判断方法をとっています。
休職は、懲戒処分のように制裁として就労を禁止するものではなく、労務に従事させることをに伴う支障を理由として発令されるものです。
休職制度の中で、一般的なものと考えられる傷病休職について、その一般的な制度をみてみますと、長期欠勤について一定期間を定めて、この期間中に治癒し就労可能となれば休職は終了し、復職することととなりますが、治癒せず期間満了となった場合、退職または解雇となります。
労働契約という観点からみますと、就労不能は、労務提供義務の不履行にあたりますから、労働契約の解約事由となります。しかし、傷病休職制度は、休職期間中の就労を免除し、病気の回復を待ち、その期間は労働契約の解消を猶予するものです。
裁判所は、傷病休職制度は、それが存在することにより、休職を命じるまでの欠勤期間中に解雇されない利益を従業員に保障したものとはいえず、使用者には、休職までの欠勤期間中に解雇するか、休職に付するかについて裁量があり、この裁量を逸脱したと認められる場合にのみ解雇権濫用として、解雇が無効となる、としています(岡田運送事件 東京地判平成14年4月24日)。
休職制度と種類について
休職についてはいくつか種類がありますが、休職期間満了時に退職・解雇が問題となるのは、傷病休職や事故欠勤休職、自己都合休職が多くなると考えられます。
つまり、休職制度はその目的や内容を異にする様々な制度が存在しますが、その制度目的が解雇猶予である場合に、休職期間満了時の退職・解雇が多く問題となっています。
休職が発令され、その休職制度が解雇猶予目的であり、休職期間が解雇猶予期間と考えられる場合には、休職期間満了時点において、復職の要件を満たしていない場合、退職もしくは解雇となります。
争点
そこで、争いとなる場合の多くは、労働者が、復職の要件である傷病等から回復しているかということになり、解雇猶予期間であることが明らかと考えられる傷病休職であれば、「治癒」しているか否かということになります。
休職期間満了時に解雇となる場合には、労働契約法16条による、解雇権濫用法理が適用されますが、傷病休職の場合、休職期間は解雇猶予期間として定められていると考えられますので、期間満了をもって、解雇とする場合には、原則として解雇権濫用とされる可能性は低いと考えられます。
ただし、労働基準法20条の適用がありますので、休職期間満了の30日前に予告するか、休職期間満了時に予告手当を支払う必要があります。
休職期間満了時に契約が自動終了となり、退職となる場合には、労基法20条、労働契約法16条の適用はありません。
しかし、そうなりますと、傷病休職の発令が、事実上解雇予告ないし条件付解雇と捉えられる可能性がありますので、その場合には、休職期間を30日以上にしておくことが必要となると考えられます。
事故欠勤休職について
事故欠勤休職におきましては、解雇猶予措置であれば、傷病休職と同様となります。
しかし、休職期間満了の際に、改めて解雇の意思表示を行うという形態であれば、この解雇の意思表示が各種立法や解雇権濫用法理等により規制されます。
期間満了の際に自然退職をもたらすものである場合などは、休職の意思表示が解雇予告の意思表示も含むことになりますので、解雇予告としてなされた場合には、予告期間に就労可能となっても期間の経過とともに解雇が発効することになります。この場合も、休職期間を30日以上にしておくことが必要となると考えられます。
傷病休職制度(精神の不調)
通常定められている欠勤制度である、傷病休職制度等に関連して、近時問題となっているものに、精神の不調、いわゆるメンタルヘルス不調があります。
精神の不調に関しましては、出勤が断続的であったり、仕事が手につかないなどの無気力状態が続いたりすることが多いです。
このような場合に、傷病休職とすることができるかは、就業規則等によることになりますので、定める際には注意が必要となります。
就業規則に、精神の疾患により業務上の必要性から休職を命じることができるような規定が存在すれば、欠勤が継続していなくても休職の発令をすることは可能と考えられています。
就業規則に、上記のような定めがない場合、断続的な欠勤を理由としては、傷病休職を発令することが困難となることが考えられます。
しかし、いかなる場合にも発令できないということではありません。
なぜならば、使用者は、労働者に対して安全配慮義務を負っています。裁判所は、労働者が現に健康を害しており、または、健康を悪化させるおそれがあると認められる場合には、使用者は、速やかに労働者を業務から離脱させて休養させる等の措置をとる労働契約上の義務を負う(石川島興業事件 神戸地姫路支判平成7年7月31日)としています。
また、労働者が医師の治療を受けず、業務に支障をきたし、職場秩序を乱しているような場合には、債務の本旨に従った労務の提供がなされていないということを理由に、使用者は、労務の受領を拒否することができるとも考えらえれます。
そうしますと、就業規則に特別の定めがなければ、病気欠勤の場合には、民法536条1項により、労働者は賃金請求権を失うとする考え方(農林漁業金融公庫事件 東京地判平成18年2月6日)もあることから、上記の労務の受領拒否も、実質上欠勤と同様に捉えることが可能となりますので、その状況が一定期間継続すれば、傷病休職を発令できるとも考えられます。
ただ、現実的には、あらかじめ就業規則等により、精神疾患をも考慮した規定を定めておくことが重要となります。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。