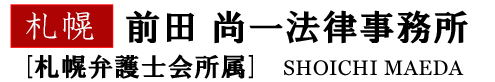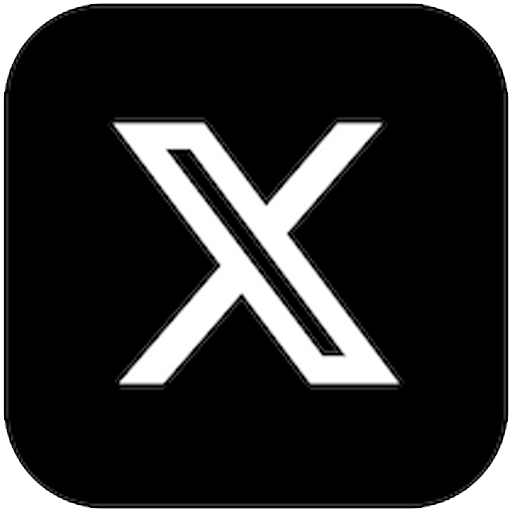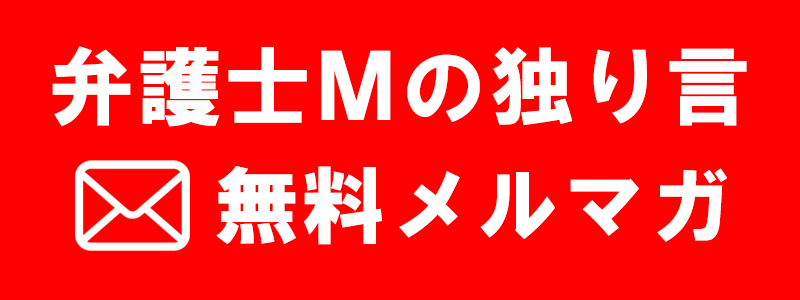持ち帰り残業
持ち帰り残業には、労働者が自宅で業務に費やした時間をいかに把握するか、また情報のセキュリティ管理ができるか、等の問題点も指摘されていますが、そもそも、労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となります。
労働基準法上の労働時間とは、最高裁判所によれば、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間と考えられています(三菱重工長崎造船所事件 最判平成12年3月9日)。
そこで、自宅で過ごすある時間が、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間といえるのかが問題となります。
その具体的な判断基準としては、ある時間の労働者の過ごし方についての使用者の関与の程度、業務性の程度が総合的に検討されています。
持ち帰り残業については、行っている内容は業務です。しかし、持ち帰り残業についての使用者の関与の程度についての態様は様々です。
使用者の関与の程度として、一般的には無関係、黙認・許容、命令・指示等が考えられます。
原則として、私生活の場である自宅は使用者の支配下にあるとはいえず、場所的拘束、時間的拘束、労務提供規律上の拘束がないため、自宅に持ち帰って業務を行ったという事実があっても、それだけでは労働時間とは評価できません。自宅が職場でもある場合でも、休息の場でもあり、客観的に使用者の拘束の度合いが低い状況下にあるため、使用者の指揮命令下にあるとは認められない可能性が高いです(日本インシュアランスサービス事件 東京地判平成21年2月16日参照)。
つまり、労働者が自発的に自宅に持ち帰って行う業務については、使用者の支配下に置かれているとはいえず、労働基準法上の労働時間には該当しないと考えられます。
しかし、使用者あるいは使用者に代わって労働者に指揮命令をする立場にある者が、労働者に命令・指示等をした場合は、その程度によっては、労働者が自宅で仕事をした時間も労働基準法上の労働時間となり得ると考えられます。
使用者の関与が、黙認・許容の段階であった場合でも、上記のように、使用者の関与の程度と業務性の程度から総合的に検討されるとすると、持ち帰り残業は業務性があることは明らかですので、労働者が自宅で労働した場合の労働時間性が肯定される可能性はあります。
そして、労働基準法上の労働時間に該当する可能性が低くても、労働時間について基準が異なると考えられる労災保険法の適用上の業務起因性の認定に当たっては、労働時間に該当する可能性はあります。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。